INTERVIEW
社員インタビュー

脱炭素社会の実現に向けて、
エネルギーキャリアの
実用化を推進。
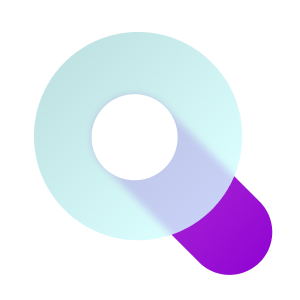
研究開発
T.N.
- 中央技術研究所 先進技術研究所 低炭素技術グループ
- 工学府修了
- 新卒採用2011年入社
2013年3月
根岸製油所 製油1グループ根岸製油所の運転管理に従事。全装置の稼働を止めてメンテナンスや改造を行う「定修」を経験。
2014年4月~現在
中央技術研究所 水素グループ有機ハイドライドと呼ばれるエネルギーキャリアに関する研究業務に従事。
現在の仕事内容は?
私が所属する先進技術研究所は、マテリアルズインフォマティクスやCFD解析といったデータサイエンスを検討するグループと、二酸化炭素を原料とした次世代燃料製造や水素エネルギーの利用を検討するグループからなります。私は低炭素技術グループに属しており、太陽光発電や風力発電などに代表される、再生可能エネルギー(再エネ)を利用するための検討を行っています。再エネは基本的に地産地消ですが、再エネに適した土地が少ない日本は海外に比べてコスト面に課題があります。そこで、安価で大量に製造可能な海外の再エネを、エネルギーキャリアに変換して日本に輸送し、国内でエネルギーを取り出して利用することが私の研究テーマです。
再エネを利用した水の電気分解によってクリーンなエネルギー源である水素を製造することが可能であり、この水素を水素と呼びます。しかし、水素は気体のままでは貯蔵や長距離の運搬効率が低いといった問題を抱えています。そこで、水素をエネルギーの貯蔵・輸送媒体であるエネルギーキャリア(水素化合物)に変換することで効率的に貯蔵・運搬することができるようになります。有望なエネルギーキャリアとしてはアンモニアや有機ハイドライドが挙げられますが、ENEOSでは石油製品の一種であるガソリンと性状が近く、石油精製技術と親和性の高いトルエン/メチルシクロヘキサン系有機ハイドライドに着目し、本格的な低炭素社会の実現を目指した研究開発を行っています。

ENEOSの有機ハイドライドの特色は?
トルエンに水素を付加させたものがメチルシクロヘキサン(MCH)であり、MCHを製造することで水素を貯蔵・運搬することができます。また、水素エネルギーの使用時はMCHから水素を取り出すことでMCHはトルエンに戻るため、エネルギーキャリアとして繰り返し利用することが可能です。これまでMCHの製造には、水電解によって水素を製造・貯蔵し、トルエンと高温・高圧条件下で反応させる2段階のプロセスが必要でした。そこでENEOSでは水とトルエンから電気化学的に直接MCHを製造する新たなプロセスとして「Direct MCH」技術を開発しました。Direct MCHプロセスでは、トルエンの電解により1段階でMCHの合成が可能なため、MCHの製造コストを大幅に低下させることが期待できます。2018年12月にはオーストラリアにおいてDirect MCHプロセスによる有機ハイドライドを低コストで製造し、日本で水素を取り出す世界初の技術検証にも成功しました。再エネに適した土地の少ない日本が低炭素社会を実現するためには、海外の再エネを安定的、かつ安全に輸入することが不可欠です。太陽光発電など再エネに適した広大な国土を有するオーストラリアでの実証実験は、水素利用技術の社会実装に向けた大きな一歩になりました。

新エネルギー研究の面白さ、難しさとは?
低炭素社会を実現するための技術検討は、環境問題解決への貢献という観点でも魅力的なテーマです。ENEOSといえば、石油精製技術をベースとして安全・安定したエネルギー供給により社会に貢献している企業というイメージがまだまだ強いと思います。そのENEOSにおいて地球環境に調和した持続可能なエネルギー供給という次のステージに向けた研究テーマに従事していること自体に大きなやりがいがあると感じています。
しかし、石油精製は歴史も長く、とても完成度の高い技術です。加えて、燃料を使うエンジンも燃費向上が続いていることから、石油由来の燃料に対して、再エネ由来のエネルギーがコスト競争力を持つには、技術革新が必要です。Direct MCHプロセスも小型装置による水素の製造には成功しましたが、実際に商用ベースに移行するには製造装置の大型化や、さらなるコスト削減が必要です。そのためには使用する触媒の改良や、各種機器の構造検討など、まだまだ研究すべき課題が山積しています。現在は収益面で会社に貢献できていない水素に関するこの技術を、近い将来、事業化させ、ENEOSの柱に成長させることが我々の目標です。

思い描くこれからのビジョンを教えてください。
現在私が研究を進めている、再エネをエネルギーキャリアに変換し、日本国内に輸送した上でエネルギーを取り出して利用するサイクルが進めば、CO₂排出量の増大を抑制することができます。しかし、世界的にエネルギー利用量が増加傾向にある現代においては、大気中に放出されたCO₂自体を回収していくことも重要と考えています。つまり、CO₂を原料とした有用物の合成や、製品の付加価値向上のためのCO₂利用技術も鍵になります。まずは、取り組んでいるDirect MCHプロセスによる水素の利活用が広く世界に展開されていくことを目指し、加えてCO₂の利用技術についても検討したいと考えています。
一日のスケジュール
| 7:30 | 長男、長女を保育園へ |
|---|---|
| 8:30 | 出社 メールチェック、実験用の薬品準備・装置起動。 |
| 9:30 | 実験開始 実験状況の観察・記録、分析装置の準備。 |
| 12:00 | 昼食 研究所の社員食堂でランチ。 |
| 13:00 | 共同開発業者との定例打合せ 前回打合せからの進捗についてお互いに情報共有。新規技術に対する特許出願について協議。次回打合せまでの検討項目確認、日程調整。 |
| 15:00 | 実験データ整理 午前中の実験結果についてデータ整理。チームミーティング用の報告資料作成。 |
| 16:30 | 翌日の実験準備 実験の後片付け(洗浄、薬品廃棄)。翌日の実験器具準備。 |
| 17:00 | 退社 |
| 18:00 | 長男、長女の保育園お迎え |
| 20:30 | フットサルに参加 子ども達の夕食・入浴を済ませてから、寝かしつけを妻に任せ、会社の班活動(フットサル)に参加。週一のデトックス。 |